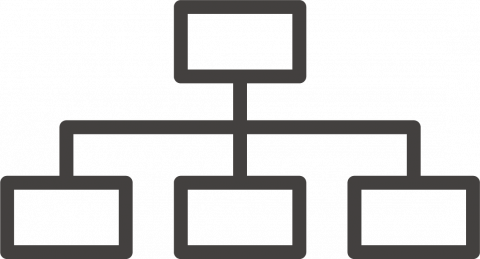センターだより
第1回 学生のための教師未来塾
第1回 学生のための教師未来塾


研修の様子
・受講生の声
千葉県総合教育センターにて、第1回 学生のための教師未来塾を行いました。未来の教師を目指す90名の受講生が集まり、積極的に演習に取組み充実した研修となりました。
・期 日 令和4年10月23日(日)
・研修テーマ1 「教員の仕事について」
講師:千葉県教育庁教育振興部教職員課 俵 大樹 管理主事
・研修テーマ2 「子供たちの『かけがえのない命』を守るために
ー 『学校安全の手引』の活用について ー 」
ー 『学校安全の手引』の活用について ー 」
講師:千葉県教育庁教育振興部児童生徒安全課 田中 福太郎 指導主事
・研修テーマ3 「今、教師に求められているもの」
・研修テーマ3 「今、教師に求められているもの」
講師:千葉県総合教育センター 鈴木 賢一 主席研究指導主事


研修の様子
・受講生の声
「教員になったら、どのようなことがしたいのか具体的に考えました。今後、教員になりたいという気持ちの向上につながりました。」
「自身が教員になった際、現場で生かせるように、あらためて学んだことを振り返り、自分なりの答えを見つけ、同じ教員を目指す仲間と高め合っていきたいと思います。」
「安全教育の知識や教師として大切な価値観を学ぶことができたので、さらに、それらを深めていきたいと感じました。」
「学校安全の講話では、実際に教員になった際、必要な内容を知ることができました。今日学んだことを活用できるよう、資料等に目を通しておきたいと思いました。」
「自分がなりたい教師像と国や県、地域や家庭、生徒が求めている教師像を学んだため、それに向かって努力をしていきたいです。」
「『なりたい教員像』と『求められる教員像』について考え、そのギャップを埋め、求められる人材になるためにどのように行動すればよいか、日々考えたいと思います。」
第3回 中堅教員サポート塾
千葉県総合教育センターにて、第3回 中堅教員サポート塾を行いました。小学校9名、中学校3名、高等学校2名、特別支援学校2名の計16名の先生方が参加しました。様々な校種の先生方が集まり、やる気あふれる研修会となりました。
・期 日 令和4年10月22日(土)
・研修テーマ1 「全国学力・学習状況調査について(結果分析と手引きの活用)」
講師:千葉県総合教育センター 峯 浩之 研究指導主事・矢部 やよい 研究指導主事
・研修テーマ2 「校内研究(研修)の進め方について」
講師:千葉県総合教育センター 竹政 崇典 研究指導主事


研修の様子
・受講生の声
「全国学力・学習状況調査の分析では、教科横断的なテーマが問題から読み取っていけることを学べたので、自分の担当教科だけでなく、他教科にも目を向けて活用していきたい。」
「全国学力・学習状況調査の活用では、授業づくりや学力向上に生かせる分析、活用が図れるよう、研究主任の先生とさらに話をしていきたいと思った。」
「高校生の学力低下も問題となっているので、今回の学力調査の話を参考に学力向上を図りたい。」
「限られた時間の中で効果的で効率的な研修を行なっていけるよう、さまざまなツールを活用していきたい。」
「小、中学校で行われている校内研究はとても重要なものだと感じた。高校ではテーマを決めて研究することはあまりしないが、研究授業などを行い、相互に授業参観をすることは大切だと感じた。」
「校内研究(研修)の進め方では、よりよい研究となるために、研究のもち方の工夫をしていきたいと思った。短い時間でも効果的なものとなるように考えていきたい。」
第3回 若い教師のためのあすなろ塾
過ごしやすい季節にもなり、第3回「若い教師のためのあすなろ塾」が予定通り開催され、29名の先生方が参加しました。今回も土曜日の午後からの半日で「主体的・対話的で深い学びの授業づくり」と「主体的・対話的で深い学びを実現するための教材研究と問い」のテーマで、授業づくりから実践方法までを研修しました。
・期 日 令和4年10月22日(土)
・研修テーマ1 「主体的・対話的で深い学びの授業づくり」
講師:千葉県総合教育センター 橋本 淳 研究指導主事
・研修テーマ2 「主体的・対話的で深い学びを実現するための教材研究と問い」
講師:千葉県総合教育センター 串田 篤典 研究指導主事


研修の様子
・受講生の声
「今まで「深い学び」とはどういうことなのか、はっきりしていない部分がありましたが、教師がどんどん問いを投げかけ、すっきり!なるほど!と子供が思えるようにするところで腑に落ちた気がします。」
「まずは「授業の振り返りの時間をきちんととること」、「最終活動を早い段階で提示して見通しを持たせること」など、普段の授業で疎かになりそうなことを意識して改善していきます。」
「まずは「授業の振り返りの時間をきちんととること」、「最終活動を早い段階で提示して見通しを持たせること」など、普段の授業で疎かになりそうなことを意識して改善していきます。」
出前中堅教員サポート塾(我孫子市8/30)
出前中堅教員サポート塾



研修の様子
・受講生の声
我孫子市において、小・中学校19校の学力向上担当(研究主任または教務主任)の先生方を対象に、「全国学力・学習状況調査について」の出前中堅教員サポート塾を開催しました。当日は講話に加え、問題分析の演習を取り入れ、参加者の皆さんは、大変熱心に取り組んでいました。
〇 我 孫 子 市
・期 日 令和4年8月30日(火)
・研修テーマ 全国学力・学習状況調査について
・期 日 令和4年8月30日(火)
・研修テーマ 全国学力・学習状況調査について



研修の様子
・受講生の声
「校内研修を経て、教科や学年を越えて分析をしていきたいです。また、他人事ではなく自分には何ができるかを考えながら授業改善をしていきたいです。」
「学力向上に向けて学校全体で生徒の実態把握をする必要性を感じました。実態を知るだけでも、授業や生徒指導に良い変化が起こると思います。」
「分析ツールや分析シートについて、今後活かしていこうと思います。またCOMPASSも全てファイリングしてますので、引き続き自分の勉強のためにも読ませていただきます。」
「正直なところ、学力向上に向けて自分自身で自校の分析をきちんとしたことがなかったので、よい機会になりました。学力調査する教科のみに任せるのではなく、自分事として受けとめたり、今後の授業改善をしていこうと前向きに考えたりすることができてよかったです。」
「分析ツールや分析シートについて、今後活かしていこうと思います。またCOMPASSも全てファイリングしてますので、引き続き自分の勉強のためにも読ませていただきます。」
「正直なところ、学力向上に向けて自分自身で自校の分析をきちんとしたことがなかったので、よい機会になりました。学力調査する教科のみに任せるのではなく、自分事として受けとめたり、今後の授業改善をしていこうと前向きに考えたりすることができてよかったです。」
出前中堅教員サポート塾(八千代市8/19、市原市8/26)
出前中堅教員サポート塾



研修の様子
・受講生の声
・受講生の声
八千代市では、「指導と評価の一体化について」「校内研究(研修)の進め方について」、市原市では、「指導と評価の一体化について」「SDGsを取り入れた教育について」の出前中堅教員サポート塾を開催しました。それぞれの演習においては、先生方はお互いに意見交換しながら、とても熱心に取り組んでいました。
〇 八 千 代 市
・期 日 令和4年8月19日(金)
・研修テーマ 校内研究(研修)の進め方について
・期 日 令和4年8月19日(金)
・研修テーマ 校内研究(研修)の進め方について



研修の様子
・受講生の声
「ルーブリック評価は一部の教科で取り入れていますが、どのような評価基準を作成したら良いのか等、難しいところがあるので、今後も学んでいきたいです。」
「「評価」をすることは、教師側としては「子供」が対象ですが、自分自身も評価していかなくてはならないという意識を現場で高めていく必要があると感じました。」
「「評価」をすることは、教師側としては「子供」が対象ですが、自分自身も評価していかなくてはならないという意識を現場で高めていく必要があると感じました。」
「校内研究の方法論について、新たな知見が得られたので、今回の研修で学んだことをもとに校内研修を進めていきたいと思います。」
〇 市 原 市
・期 日 令和4年8月26日(金)
・研修テーマ SDGsを取り入れた教育について



研修の様子・期 日 令和4年8月26日(金)
・研修テーマ SDGsを取り入れた教育について



・受講生の声
「初めてSDGsのことについて詳しく学ぶことができました。9月からどのようなことが自分にできるのか、子供たちにはどのように伝えていけば良いのかを考えていきたいです。」
「評価をより工夫し、授業をより良くしていこうと思います。また、ESDを念頭に、授業の題材や展開を工夫していきたいと思います。」
「具体的に何をやったらよいのかがわかりました。9月から生かしていきます。
「評価をより工夫し、授業をより良くしていこうと思います。また、ESDを念頭に、授業の題材や展開を工夫していきたいと思います。」
「具体的に何をやったらよいのかがわかりました。9月から生かしていきます。
最新の教育内容をどのように理解し、日頃の実践に生かしていくか、日々考えていきたいと思いました。」